外壁塗装で人気のツートンカラー!おしゃれに仕上げるコツと塗り分けパターン
公開:2024.08.15 更新:2024.08.27
ツートンカラーは、外壁塗装で人気のスタイルであり、住宅の外観に個性と深みを与える効果があります。ツートンカラーの塗り分け方には、上下階での分け方や、縦方向に分ける方法、ベランダなどの出っ張り部分をアクセントにする方法があり、それぞれ異なる効果を生み出します。
特に日本の住宅では、上下階や左右で色を分けることで立体感を強調し、視覚的なバランスを保ちながら、印象的な外観を作り出せます。
ツートンカラーの魅力は、その視覚的効果だけでなく、周囲の環境や住む人の個性に合わせて柔軟に対応できる点にもあります。例えば、自然と調和する落ち着いた色合いや、明るい色を選ぶことで、家全体の印象を大きく変えることができます。
ただし、ツートンカラーの色選びでは、使いすぎや濃い色の扱いに注意が必要です。バランスを取ることで、より魅力的な外観を実現できます。
目次
外壁塗装で人気のツートンカラー
和歌山で外壁塗装の予定がある方の中には、ツートンカラーを検討している方も多いでしょう。外壁塗装において、ツートンカラーは昔から定番であり、現在でも非常に人気の高いスタイルです。
ツートンカラーは、住宅の外観に変化と深みを加えることができ、個性を表現するのに最適な手法です。なぜツートンカラーがこれほどまでに支持され続けているのか、その理由を解説します。
◇人気の高いツートンカラー
ツートンカラーは、住宅の外観に立体感を持たせるための効果的な方法として広く用いられています。特に日本の住宅では、シンプルながらも個性を表現できるこのスタイルが長く愛されてきました。
例えば、上部と下部、もしくは左右で色を分けることにより、建物全体に動きが生まれ、視覚的なバランスを保ちつつも、見る人に強い印象を与えられます。
また、ツートンカラーは新築住宅だけでなく、リフォームや外壁の塗り替えの際にも人気があり、時代を超えて多くの人々に支持されているデザインです。
◇ツートンカラーが人気の理由
ツートンカラーの人気の理由として、第一に挙げられるのは、その視覚的効果です。異なる色を組み合わせることで、建物の立体感が強調され、外観にメリハリがつきます。これにより、同じ建物でも色の使い方次第で全く異なる印象を与えられます。
さらに、ツートンカラーは周囲の環境や住む人の個性に合わせて柔軟に対応できる点も魅力です。例えば、周囲の自然と調和する落ち着いたカラーを選ぶことで、風景に溶け込みやすくなり、一方で明るい色を選べば、家全体が際立ち、目を引く存在になります。
これらの点が、ツートンカラーが長年にわたり支持されてきた理由です。
ツートンカラーの塗り分けタイプ

ツートンカラーの外壁塗装では、色の分け方が仕上がりの印象を大きく左右します。ここでは、代表的な塗り分けタイプについて解説し、それぞれの方法が持つ特徴や効果を紹介します。
◇上下階で分ける
ツートンカラーの塗り分け方として最も一般的なのが、上下階で色を分ける方法です。例えば、1階部分を濃い色、2階部分を淡い色にすることで、建物全体に安定感を与えられます。
この方法は、視覚的な重心を下げる効果があり、家全体がしっかりと地に足をつけているような印象を与えます。
また、逆に上部を濃い色にすると、建物が軽やかに見えるため、周囲の風景に馴染みやすいという特徴もあります。この塗り分け方法は、どのような住宅にも適応しやすく、万人受けするスタイルと言えるでしょう。
◇縦方向に塗り分ける
次に、縦方向に色を分ける方法があります。縦に色を分けることで、建物が高く見える効果を生み出し、視覚的な伸びやかさを演出します。
この方法は、特に背の低い平屋建ての住宅や、横に長い建物に適しており、垂直方向へのラインを強調することで、建物がすっきりと見える効果があります。また、異なる素材やテクスチャーを組み合わせることで、より一層個性的な外観を実現することも可能です。
◇ベランダなど出っ張りのある部分を塗り分ける
最後に、ベランダや出っ張り部分を塗り分ける方法です。この方法では、建物の凹凸や突出部分に異なる色を使うことで、外観にリズム感を与えられます。
例えば、ベランダ部分をアクセントカラーにすることで、建物全体が引き締まり、立体感が増します。また、窓枠や柱などの細かい部分にも異なる色を施すことで、デザイン性の高い外観を実現することができます。
このような塗り分けは、建物の特徴を引き立て、より一層魅力的な外観に仕上げるための有効な手段です。
ツートンカラーの色選びの注意点
ツートンカラーで外壁塗装を行う際には、色選びが重要なポイントです。適切な色を選ばなければ、全体のバランスや仕上がりが崩れてしまう場合もあります。ツートンカラーの色選びにおける注意点を解説します。
◇色を使い過ぎない
ツートンカラーに多くの色を使うと、ごちゃごちゃとした印象を与えてしまい、全体の統一感が失われてしまうことがあります。
そのため、ツートンカラーでは基本的に2色、場合によってはアクセントカラーとしてもう1色を追加する程度に留めるのが理想的です。3色程度であれば、外観全体がシンプルでありながらも洗練された印象を保てます。
◇濃い色は難易度が高い
ツートンカラーで濃い色を使う場合、その選択には慎重を期す必要があります。濃い色は家全体を引き締める効果がありますが、使い方を間違えると、建物が重々しく見える、あるいは目立ちすぎてしまうことがあります。
また、濃い色は退色しやすく、汚れが目立ちやすいというデメリットもあります。そのため、濃い色を使用する際は、どの部分に使うか、どの程度の面積にするかをよく考えることが重要です。
◇同系色でぼやけることがある
同系色を使ったツートンカラーは、調和が取れやすく、失敗しにくいという利点がありますが、注意が必要です。同系色を選ぶ際、色味が近すぎると、全体がぼやけた印象になり、ツートンカラーのメリハリが失われてしまうことがあります。
そのため、同系色を選ぶ場合は、微妙にトーンが異なる色を選ぶ、あるいは片方を少し濃い目の色にするなど、バランスを取る工夫が必要です。同系色であっても、色の選び方次第でしっかりとしたツートンカラーの効果を得られます。
おしゃれなツートンカラーを実現するコツ
ツートンカラーで外壁塗装を成功させるためには、色の選び方や比率、そして全体のバランスが重要です。ここでは、おしゃれなツートンカラーを実現するためのコツを解説します。
◇色分けの比率
ツートンカラーを取り入れる際、色分けの比率は非常に重要です。
理想的な比率は、全体の7割をメインカラーにし、残りの3割をサブカラーにするというものです。この比率を守ることで、全体のバランスが良くなり、落ち着いた印象を与えられます。3色を使う場合は、70:20:10の比率を目安にすると良いでしょう。
このような比率を守ることで、複数の色を使っても統一感を失わず、デザイン性の高い外観を実現することができます。
◇調和のとれた同系色を選ぶ
ツートンカラーを選ぶ際、調和のとれた同系色を選ぶことがポイントです。同系色は、自然なグラデーションを生み出し、建物全体に統一感を持たせられます。また、同系色を選ぶことで、外観が落ち着いた印象になり、長く飽きのこないデザインに仕上げられます。
特に人気の組み合わせとしては、グレーとホワイト、ベージュとブラウンなどが挙げられます。これらの色は、どのような建物にも合わせやすく、失敗が少ないため、迷った際にはこれらの色を選ぶと良いでしょう。
ツートンカラーの外壁塗装における魅力の一つは、色の組み合わせによって住宅の外観に変化を持たせることができる点です。例えば、上下階や左右で色を分けることで、建物全体に動きが生まれ、視覚的なバランスが取れた印象を与えます。
ツートンカラーの人気が衰えない理由として、視覚的な効果が挙げられます。異なる色を組み合わせることで、建物の立体感が強調され、外観にメリハリが生まれます。これにより、同じ建物でも色の使い方次第でまったく異なる印象を与えることが可能です。
ツートンカラーの塗り分け方にはいくつかの方法があり、それぞれが異なる効果を生み出します。上下階で色を分ける方法は、建物に安定感を与える効果があり、視覚的にしっかりとした印象を持たせることができます。逆に、上部に濃い色を使うと、建物が軽やかに見え、周囲の風景に馴染みやすくなります。
縦方向に色を分ける方法は、建物が高く見える効果を生み出し、特に背の低い平屋建てや横に広がる建物に適しています。さらに、ベランダや出っ張り部分を異なる色で塗り分けることで、外観にリズム感を加え、立体感を強調することができます。
ツートンカラーで外壁塗装を行う際には、色選びが非常に重要です。適切な色の組み合わせを選ばないと、全体のバランスが崩れるなど、意図しない仕上がりになることがあります。
濃い色を使う場合は、その選択に慎重を期する必要があります。濃い色は建物全体を引き締める効果がありますが、使い方を間違えると、重々しい印象になる、あるいは目立ちすぎてしまうことがあります。さらに、同系色を使う場合は、微妙なトーンの違いを意識して選ぶことで、しっかりとしたツートンカラーの効果を得ることができます。
ただし、色を使いすぎると、建物がごちゃごちゃとした印象になり、統一感が失われることがあるため、基本的には2色、場合によってはアクセントカラーを加えた3色程度に抑えるのが理想的です。 理想的な色分けの比率は、メインカラーを全体の7割、サブカラーを3割とすることです。この比率を守ることで、全体のバランスが良くなり、落ち着いた印象を与えられます。
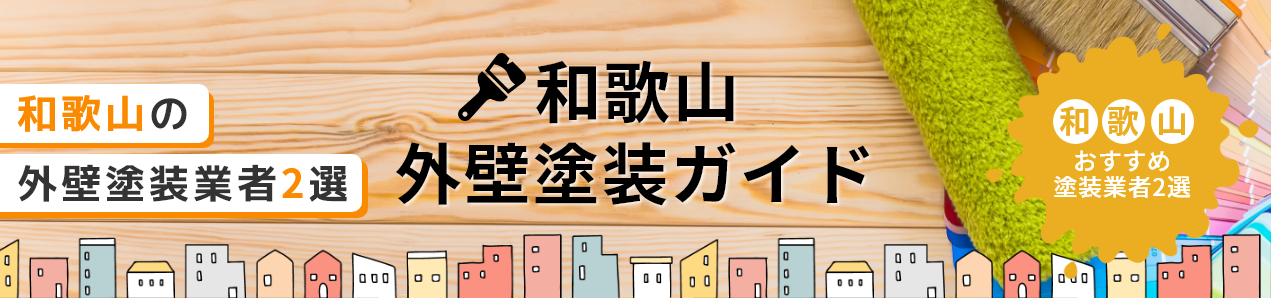
 和歌山 外壁塗装ガイド
和歌山 外壁塗装ガイド 